ブログ
Blog

Blog
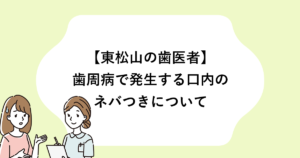
歯周病の主な症状としては、歯茎の腫れが挙げられます。
その他歯茎から出血したり、歯と歯の間の隙間が大きくなったりすることも、代表的な症状です。
また、朝起きたとき、口内のネバつきがひどくなるケースもあります。
今回は、歯周病で発生する口内のネバつきについて解説します。
歯周病で発生する口内のネバつきは、歯肉溝浸出液と呼ばれるものです。
こちらは、歯周病に感染したときに分泌される液体です。
一般的に、口内がネバついている場合、ストレスや体調不良などが原因となっているケースが多いです。
しかし、毎日のようにひどいネバつきに悩まされている場合、歯周病が原因の可能性が高いです。
また歯肉溝浸出液には非常に粘度が高いという特徴があり、歯周病の発症時は唾液の分泌量が減少しがちであるため、口内に占める歯肉溝浸出液の割合が増加します。
その結果、さらにネバつきがひどくなるという悪循環が生まれます。
歯周病によって口内のネバつきがひどいにもかかわらずそのまま放置していると、口臭や虫歯のリスクが高まります。
こちらは、唾液が減少することで口内の自浄作用、殺菌作用が低下するからです。
また、誤嚥性肺炎のリスクも高くなるおそれがあります。
誤嚥性肺炎は、本来気管に入ってはいけない細菌などを誤って飲み込んでしまうことにより、発症する肺炎です。
口内がネバつくと、唾液が減少して食べ物がスムーズに胃へ運ばれないため、誤嚥性肺炎は起こりやすくなります。
さらに口内がネバついて乾燥すると、舌にある味蕾へと食べ物の成分が届けられず、味を感じにくくなることもあります。
歯周病によって生じる口内のネバつきは、食べた後にすぐブラッシングをしたり、唾液腺を刺激したりすることである程度改善されます。
歯面や歯と歯茎の境目などの汚れを落とすことで、口内の歯肉溝浸出液の量は少なくなります。
唾液腺の刺激に関しては、酸っぱいものを食べたり、よく噛んだりすることで行えます。
またガムを噛んだり、禁煙をしたりといった方法も効果的です。
歯周病によって口内がネバネバすると、歯周病以外の感染症のリスクも高まります。
また、朝起きたときに毎回気持ち悪さを感じるようになりますし、口臭については周りの方にも影響を及ぼすことが考えられます。
歯周病は自覚症状が少ないため、なかなか発症に気付かないケースも多いです。
口内のネバつきは、歯周病の症状の一つであるため、違和感を覚えたらすぐに歯科クリニックに相談してください。